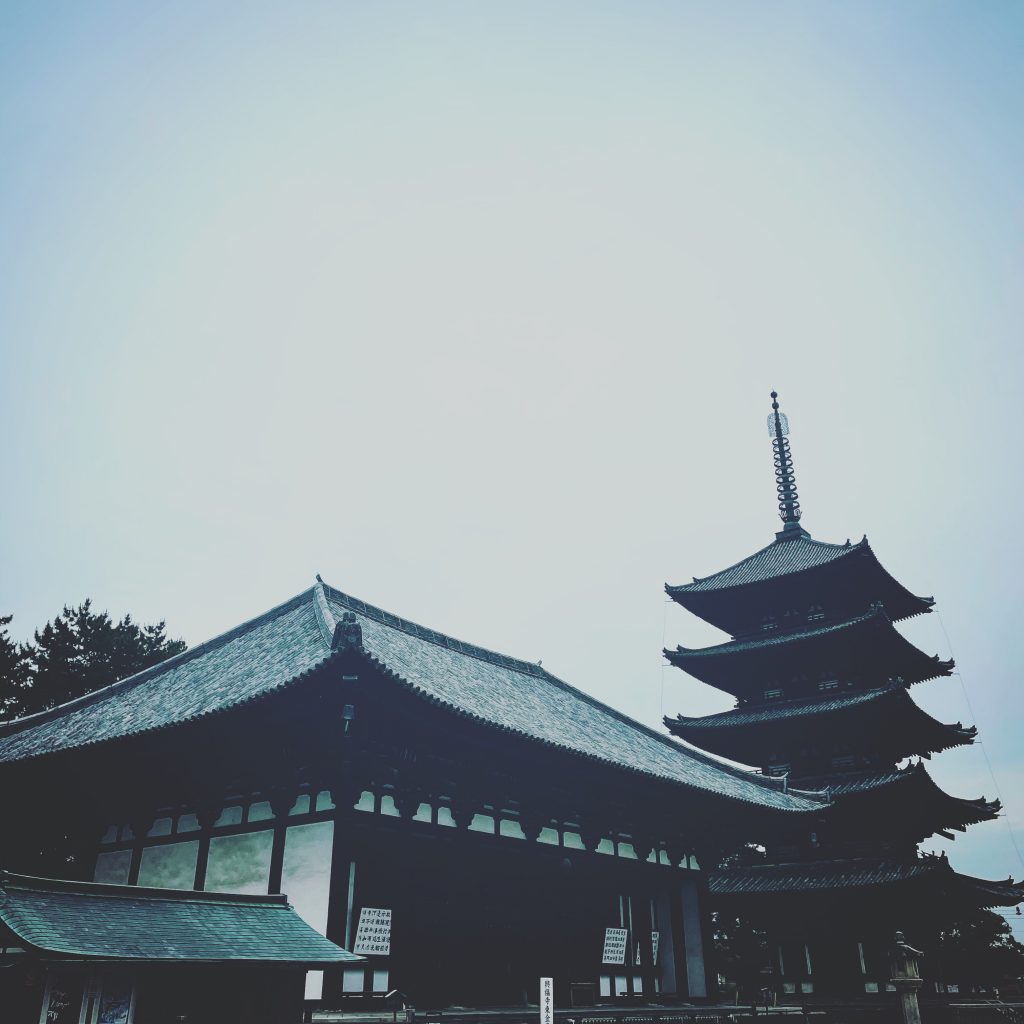
いまになって思うことだが、一九六〇年代の欧米における、いわゆる言語論的転回を日本で受容した層は、まずまちがいなく「転回」など感じていなかった。歴史は科学か、という問いをつきつけたマックス・ウェーバーにはじまって、歴史は歴史家によって作られたものではないか、という構築主義的な懐疑が最初から学者の心のどこかに存在しており、その素朴かつ漠然とした懐疑が欧米のlinguistic turnのおかげで理論的な装いを得ただけで、実際には「転回」というべき衝撃はなく、むしろ懐疑に対する大人の賛同のように機能したのではないだろうか。
◆
言語論的転回を信じて一番ダメージを受けるのは歴史学者である。しかし——というよりだからこそ、昨今の日本の歴史学者は多少の一瞥はくれてもほとんど無関心だし、歴史上の事実そのものではなく、いくつかの事例の差異を論じる社会学者にはノーダメージだから、これを問題なく受け入れる。要するに、転回はなにも起こっていないのである。
◆
星や鳥や木々のように歴史を愛した自分からすれば、言語論的転回は、ぼくの思考を完全に破壊した。だからクライストのように落ち込んだ。しかしおそらく、ほんとうに真面目にこの問題に取り合った日本人は、ほとんどいないのではないだろうか。モダンとポストモダンのはざまで、20代のぼくは取り残されていた。
実証を夢見て歴史に取り組み、それがついに夢に終わることを知らされた自分には、将来の道がまったく見えなくなった。おかげさまで10年くらい、ぼくの精神生活は危機的状況に陥ったのだが、とにかく浅薄な(当時のぼくにはそう見えた)連中が言語論的転回に飛びつき、いままた実在論に飛びついているのだから、その変わり身に驚く。
こういう連中は、べつに転回などしておらず、たんに氷上でふらふらしているだけだと思うが、一方でぼくは、ほんとうにくるくる回った。自分の意志ではないから、もちろん優雅ではなく、まったく哀れといっていい。氷に穴が開くくらい回ったら、ようやく止まった、しかし今度は下層の水に溺れた、という感じだ。
ヨーロッパに感心するのは、経験論でも観念論でも、どうみても片側にしか車輪のない車をとにかく走らせ、行き着くところまで行き着くことだ。両者のあいだで簡単に弁証法など働かせない。実証主義でも言語論的転回でも、壁を突き抜けて反対側に出るくらいまでやるのでないと、ほんとうは弁証法にもならない、と思う。
◆
自分は言語論的転回の渦から抜け出すのに10年かかった。まだときどきわからなくなる、ほんとうに抜け出せたのか。それが正直なところだ。元気なときは、たしかに自分は実証的だ、と思える。だが元気がなければ、自分が言っているだけではないか、と思う。実証主義といい、言語論的転回といい、そうした歴史家の不安定な精神状態の産物である、というだけのことかもしれない。要は、歴史家には元気が必要だ、ということにちがいない。……これは案外、真理である。
◆




